イドカバネット > 日本の“おもてなし”文化の一つ お客様をあたたかく迎える「おしぼり」
きれい
2021/07/21
日本の“おもてなし”文化の一つ お客様をあたたかく迎える「おしぼり」

いよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開幕します。
本来であれば、世界中からたくさんの人が訪れ、大変な盛り上がりとなるはずの大イベントですが、コロナ禍ではそうもいきません。
日本の文化である「おもてなし」を体感していただく良い機会でもあったのに、残念です。
おもてなしといえば、飲食店などで出される“おしぼり”もその一つ。
海外で食事をすると、ナプキンはあっても濡れたおしぼりが出てくることはなく、食事前に「おしぼりで手を拭きたい!」という衝動にかられます。(中国でおしぼりが出ることはありましたが、有料でした)
暑い季節はキンキンに冷やし、寒くなれば温めてお客様を迎える。
おしぼりは日本特有のおもてなしなのです。
下に続く
電車内や人混みなど
マスク着用を気にする場面など「エチケット用」として最適
呼吸がしやすく、蒸れないクールエアマスク「Be*AIR」

宅配・保管クリーニング(ラクリ)
東日本おしぼり協同組合のHPによると、おしぼりの歴史は、『古事記』や『源氏物語』の時代まで遡るそうです。お公家さんが客人を家に招く際に、濡れた布を出して迎えました。
江戸時代には、旅籠(はたご)の玄関先に水を張った桶と手ぬぐいが用意され、客は手ぬぐいを桶の水に浸してしぼり、汚れた手や足をぬぐいました。
この“しぼる”という行為が、おしぼりの語源になったと言われているそうです。
戦後、おしぼりは多くの飲食店等で出されるようになりましたが、時代の流れとともに、使い捨ての紙おしぼりが増えていきました。
紙製は、最近こそ一部、再生紙が使われることもありますが、やはり廃棄するゴミが問題になっています。
一方、布おしぼりはキレイに洗って、くり返し利用するので、ゴミ減量で環境に優しく、今の時代に合ったサービスといえます。

(布おしぼりを高速で巻いて包装する機械)
飲食店等におしぼりをレンタルする専門工場では、厳しい衛生基準による洗浄と消毒が行われ、また最近では、抗菌・抗ウイルス加工のおしぼりも登場しています。
コロナが収束し、また世界中から多くの観光客が日本を訪れるようになったら、冷たいおしぼり・温かいおしぼりを用意して、迎えてあげたいですね。
この記事を書いた人
 日笠京介(Kyosuke Hikasa) 日笠京介(Kyosuke Hikasa)ゼンドラ株式会社・取締役 リネンサプライ工場の取材をメインに、全国(たまに海外も)を飛び回るが、最近はコロナで出張もできず飲みにも行けず、悶々と過ごしている。愛犬(バーニーズ)が唯一の癒し。 |
日笠京介の最新記事
-
SDGs~つくる責任つかう責任~ 衣類購入→リサイクルの循環サイクルを少しだけ延ばす
 2021/07/09
2021/07/09 -
ロボット技術で社会が変わる 障害ある人たちの雇用を創出する“分身”
 2021/06/29
2021/06/29 -
国民によって価値観が違う「キレイの基準」って難しいです
 2021/06/17
2021/06/17 -
ペット用品のお洗濯 洗濯機か手洗いか、それともコインランドリー⁉
 2021/06/07
2021/06/07 -
タオルのイヤなニオイをなんとかしたい!プロがやるのは「80℃・10分」の“消毒”です
 2021/05/26
2021/05/26 -
コロナ禍の巣ごもり生活 ホテルのシーツが恋しい!?
 2021/05/14
2021/05/14
Facebookで更新情報をチェック!
関連記事
記事ランキング
-
食べ物や飲み物を洋服にこぼした時の適切な対処法
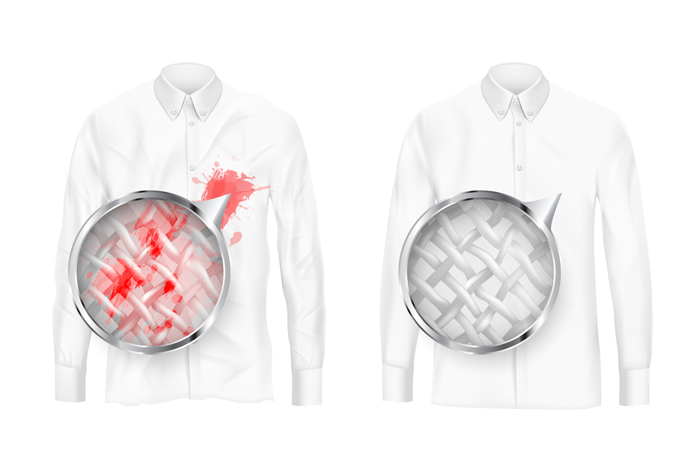 2017/12/08
2017/12/08 -
今年の大掃除 「生産性向上宣言」その1・ガスレンジ編
 2017/12/07
2017/12/07 -
ウールやシルクなど、プロが教えるデリケート衣類の洗い方
 2017/12/05
2017/12/05 -
汗やニオイがつきやすい冬のストール・マフラーの手洗い洗濯方法
 2017/12/04
2017/12/04 -
洋服をしまう前にクリーニングする理由は ドライクリーニングと水洗いの特性
 2017/11/04
2017/11/04 -
ゴシゴシ体を洗っている方は要注意!肌に優しい入浴の豆知識
 2017/10/24
2017/10/24 -
柔軟剤を入れているのに何故かゴワゴワする 原因はこれだ!!
 2017/10/22
2017/10/22 -
アイロンがけが超ラクになるシャツの洗濯テクニック!
 2017/09/11
2017/09/11 -
洗濯しても取れないTシャツやタオルの嫌な臭いを取り除く方法
 2017/08/28
2017/08/28 -
たたむ方が良い・たたまない方が良い衣類の見分け方
 2017/08/21
2017/08/21




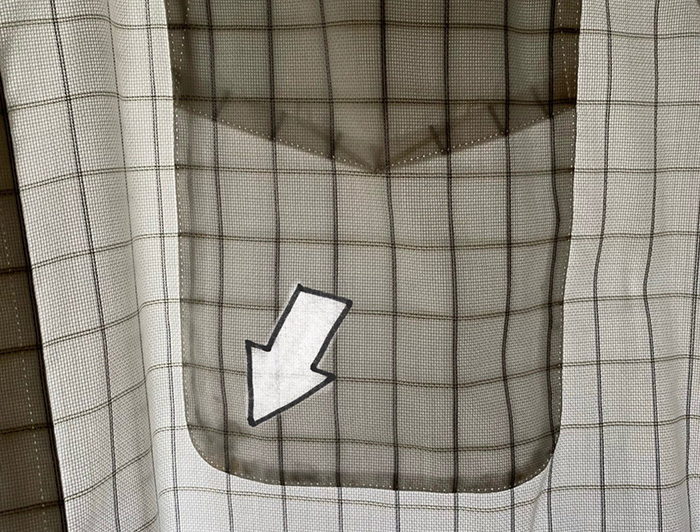


 Yシャツをきれいにたたむプロの技と旅行のパッキングのコツ
Yシャツをきれいにたたむプロの技と旅行のパッキングのコツ GW中にすませたい!部屋とクローゼットのデトックス
GW中にすませたい!部屋とクローゼットのデトックス 今すぐ実践!自宅でできる白シューズの正しいお手入れ!
今すぐ実践!自宅でできる白シューズの正しいお手入れ! 洗って完璧!柔軟剤で引き寄せない!洗濯でできる花粉症対策
洗って完璧!柔軟剤で引き寄せない!洗濯でできる花粉症対策 乾きにくい冬の洗濯物を3倍乾きやすくする干し方のコツ!
乾きにくい冬の洗濯物を3倍乾きやすくする干し方のコツ! これでイライラ0%!! ファスナーの滑りを良くする方法
これでイライラ0%!! ファスナーの滑りを良くする方法 結婚前に知っておきたい女を磨く洋服の知識・ウール製品の洗いかた
結婚前に知っておきたい女を磨く洋服の知識・ウール製品の洗いかた 面倒なんて言わせない 大切なお洋服を守る これで完璧!収納法
面倒なんて言わせない 大切なお洋服を守る これで完璧!収納法 こんなところも大掃除…誰でも簡単にできる”洗濯機の洗濯”
こんなところも大掃除…誰でも簡単にできる”洗濯機の洗濯” 色移り解消の魔法の呪文「すぐに濃いめの熱いお湯」
色移り解消の魔法の呪文「すぐに濃いめの熱いお湯」 痩せて見える/ふっくら見える 色と見た目の深い関係・1
痩せて見える/ふっくら見える 色と見た目の深い関係・1 ニッポンのすべての女性に!衣替えで役立つ「3秒ルール」
ニッポンのすべての女性に!衣替えで役立つ「3秒ルール」 洗濯物臭くないですか?部屋干しニオイ対策は、まず洗濯槽の洗浄を
洗濯物臭くないですか?部屋干しニオイ対策は、まず洗濯槽の洗浄を 型崩れ防止をできる 長期収納向けのハンガーとはどんなもの?
型崩れ防止をできる 長期収納向けのハンガーとはどんなもの? 実はめっちゃ汚い!!一枚のバスタオルを何日使いますか?
実はめっちゃ汚い!!一枚のバスタオルを何日使いますか? つい持ち歩きたくなる?ニットのほつれを瞬時に隠す「魔法の針」
つい持ち歩きたくなる?ニットのほつれを瞬時に隠す「魔法の針」 エステなどオイルまみれのタオルをスッキリきれいにするには
エステなどオイルまみれのタオルをスッキリきれいにするには ニットを着る人には知っていて欲しい素材の特徴とお手入れ方法
ニットを着る人には知っていて欲しい素材の特徴とお手入れ方法 100均アイテムで作れる超かんたんミサンガのつくり方
100均アイテムで作れる超かんたんミサンガのつくり方 荷物を軽量に!キャンプや旅先で役立つお洗濯グッズ
荷物を軽量に!キャンプや旅先で役立つお洗濯グッズ